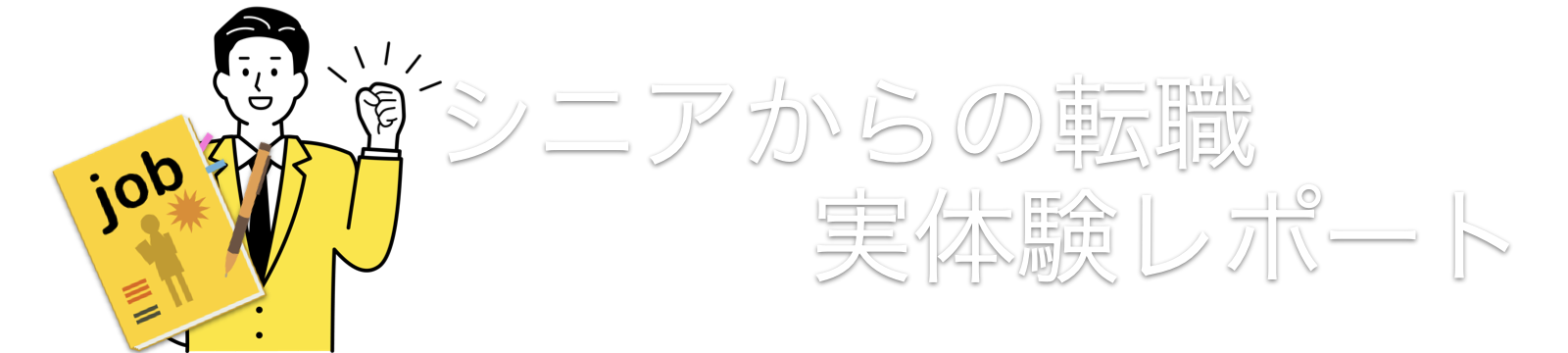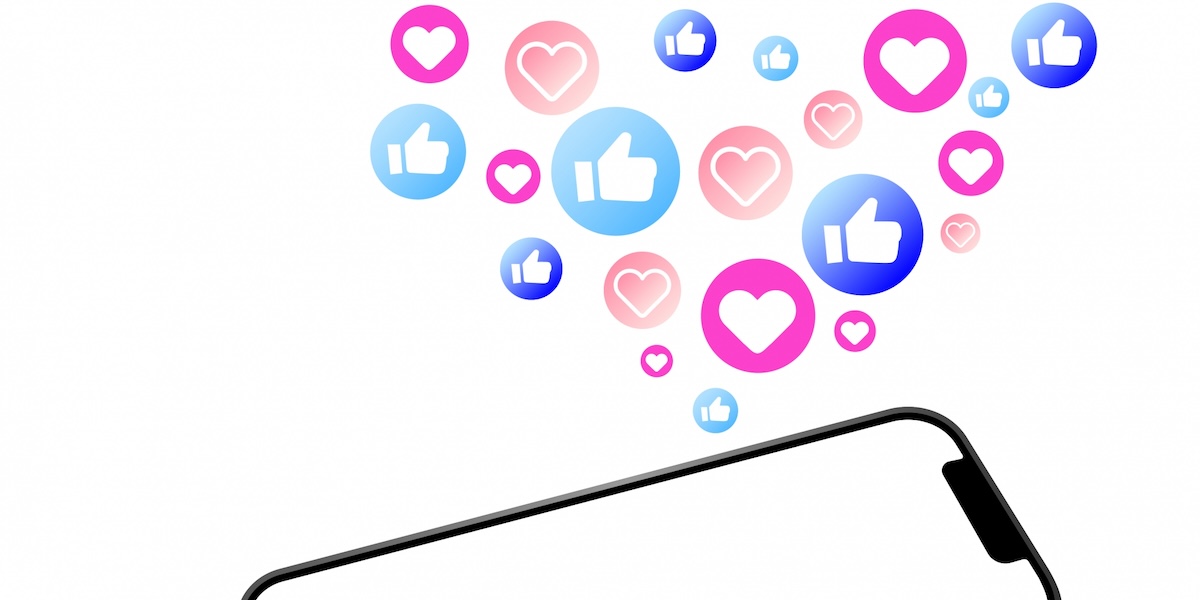「定年退職後、毎日が日曜日…」そんな夢のような日々を想像していたはずが、いざその日を迎えると、なんだか物足りない。社会とのつながりが薄れた気がするし、時間を持て余す日々に少し戸惑いを感じる。これは、私が60歳で退職した時に感じた率直な気持ちです。しかし、そんな中で出会ったのが”note”という文章発信のプラットフォーム。特別なスキルがなくても、自分の体験や思いを誰かに届けられる。さらに、工夫次第で収益化も可能です。本記事では、私自身の体験を元に、スキルがないと悩んでいるシニアの方でも安心して始められる「noteによる在宅ワーク」の始め方をご紹介します。ブログとnoteの違いや、文章生成AIの活用法、そしてリアルな体験談も交えながら解説いたします。
1、シニアの在宅ワーク入門:noteなら気軽に始められる

退職後に「自宅で何か収入を得たい」「社会とつながりを持ち続けたい」と考えるシニアは増えています。しかし、パソコンに不慣れで「何をしたら良いのか分からない」と悩む方も多いのが現実です。そんなとき、頼りになるのが「note」という情報発信サービスです。
(1)noteなら簡単投稿
noteは、スマートフォンやパソコンで簡単に記事を投稿できるプラットフォーム。特別な技術や知識は一切不要で、登録も無料。書きたい内容を入力して「公開」ボタンを押すだけで全世界に自分の文章を発信できます。
例えば、日々の暮らしの工夫や、昔懐かしいエピソード、趣味の話、定年後のライフスタイルについての知恵など、自分にとっては当たり前のことが、多くの人にとって貴重な情報になります。読者から「共感した」「参考になった」といったリアクションを得られると、自信と喜びに変わり、それが次の執筆への原動力になります。
(2)noteならSNSのようなつながり
noteには「スキ」や「フォロー」機能があり、SNSのように読者とつながることができます。また、有料記事の販売や「サポート(投げ銭)」の機能もあり、文章を通して収入を得ることも可能です。たとえ少額であっても、自分の言葉が価値あるものとして評価される体験は何にも代えがたいものがあります。
(3)noteなら既にデザインが統一されている
noteは文字の見た目も美しく、読みやすいデザインで統一されているため、レイアウトや装飾に時間をかけずに、文章の中身に集中できます。読者の閲覧履歴やリアクションが可視化されることで、何が読まれているかがひと目でわかるのも、継続するうえでの大きなモチベーションにつながります。
「難しそう」と感じている方こそ、noteのシンプルさを一度体験してみてください。最初の一歩を踏み出すことで、新たな自分の可能性が見えてくるはずです。
2、ブログとnoteの違いとは?それぞれのメリット・デメリット

ブログとnote、どちらも文章を発信し収益につなげられる人気のツールですが、その特性には明確な違いがあります。
シニアがこれから始めるなら、まず自分の目的やライフスタイルに合ったものを選ぶことが大切です。
(1)note活用術メリット
- 操作が直感的で、パソコン初心者でも安心
- アカウント作成後すぐに執筆・公開が可能
- 記事が自動で美しく整うデザイン性
- 「スキ」や「フォロー」などSNS的なリアクションでつながりが生まれやすい
- 有料記事の設定や「サポート」機能で、すぐに収益化を試せる
Noteは、パソコン操作が不慣れな方でも、ほぼ迷うことなく使える点が最大の魅力。ブログのような煩雑な初期設定やテーマ選びに頭を悩ませる必要がありません。読者との距離が近く、共感されやすい仕組みになっているため、人生経験や心の声を伝えるのに適しています。
(2)note活用術デメリット
- 検索エンジン(Googleなど)からのアクセスが得にくい(SEOに弱い)
- デザインや機能のカスタマイズがほとんどできない
- アクセス解析が簡素で細かな分析には不向き
noteは「書くことに集中する」には最適ですが、情報発信を本格的にビジネス化したい場合は少し機能不足を感じることもあるでしょう。
(3)ブログのメリット
- 自由にデザインを変更でき、自分好みのサイトが作れる
- 検索流入(SEO)を意識した記事で、長期的にアクセスを集められる
- Google AdSenseやアフィリエイト広告の設置が可能で、多様な収益化手段がある
- WordPressなどを使えば、記事やカテゴリーの構成を自在にコントロールできる
ブログは長期的な視点で育てる「資産型」のメディアとして有利です。テーマを絞って専門性の高い記事を発信すれば、継続的に収益を得る可能性が広がります。
(4)ブログのデメリット
- 初期設定(レンタルサーバー、ドメイン取得、WordPressのインストールなど)に手間と費用がかかる
- デザインや操作にある程度のITリテラシーが求められる
- 結果が出るまでに時間がかかり、途中で挫折する人も
このように、noteは「まず書き始めたい」「気軽に発信してみたい」シニアにぴったり。一方、ブログは「長期的に収益を得たい」「情報発信を仕事にしたい」という方に向いています。
私自身の体験からも、記事作成に慣れるまではnoteを使うことを強くおすすめします。理由は明確で、noteはとにかく操作が簡単でまずは「書くこと」に集中できるからです。
文章作成の習慣を身につけたり、自分の書きたいテーマを見つけるには、noteの環境が最適です。また、読者の反応がダイレクトに届くので、モチベーションも維持しやすく文章力も自然と磨かれていきます。
【体験談1】私はアフリエイト収入に魅力を感じて、最初っからブログから始めましたが、記事を書くまでの準備期間(設定など)やアフィリエイトについての理解などに時間を取られ、過去に2回ブログを失敗して今のブログが3回目の正直となりました。
そんな経験から、最初はnoteから始め、ある程度自信と経験がついてからブログに挑戦することをオススメします。noteにしてもブログにしても記事を書くことが目的で、読者が記事を読んで悩みや問題を解決できてこそ有益な記事です。執筆ペースやテーマの絞り込みができればブログの運営にもスムーズに入ることができます。
このように、noteでのスタートは「発信力」と「継続力」を育てる第一歩として非常に効果的です。そして、その先にあるブログはより自由度の高い発信や収益化へのチャレンジの場として捉えると良いでしょう。
(5)note利用者状況
①noteの利用者数と年齢層
2025年3月時点でのnoteのユーザー統計データによると、登録アカウント数は約900万、稼働アカウント数は約45万と報告されています。 年齢層の分布は以下の通りです。以下のデータから、シニア層(55歳以上)の利用者は全体の約10%で大きなチャンスです。現役時代の豊富な体験談を中心とした情報発信は、現代の若年層には貴重な情報となります。
| note利用年齢層 | note利用年齢層率 |
|---|---|
| 18-24歳 | 約21% |
| 25-34歳 | 約35% |
| 35-44歳 | 約23% |
| 45-54歳 | 約11% |
| 55-64歳 | 約6% |
| 65歳以上 | 約4% |
②他のブログサービスとの比較
主要なブログサービスであるAmebaブログのユーザー属性を見てみると、女性ユーザーが来訪者の75%を占め、その中でも30~50代が中心となっています。 また、既婚で子供を持つ女性の来訪者は718万人で、日本国内のママの約2人に1人がAmebaブログを利用している計算となります。
これらのデータから、Amebaブログは30~50代の女性、特にママ層に強い支持を得ていることがわかります。 一方、noteのユーザー層は20~40代のビジネスパーソンが大半を占めており、シニア層の利用割合はAmebaブログよりも低い傾向にあります。
③note利用者状況まとめ
noteは若年層から中年層のビジネスパーソンに支持されており、シニア層の利用者は全体の約10%と比較的少ない状況です。 一方、Amebaブログは30~50代の女性、特にママ層に強い支持を得ています。 これらのデータから、各ブログサービスは異なるユーザー層にリーチしていることがわかります。
3、私のnote体験記:10記事で得た小さな成功と学び
(1)noteを始めた理由

私がnoteを始めたのは、実はつい最近の2月からで丁度1ヶ月が経ちました。ブログ記事を書いていて、別に”自身の経験談を中心に書くことだけに専念でき、あるジャンルに特化した”情報発信をしたいと思ったからです。
Noteは書くことに特化しているので、1ヶ月で7記事書け、”いいね”が約200個、フォロワーも約130個もらえブログでは考えられないくらいの加速感です。これがモチベーションの維持に繋がっています。新しくブログを立ち上げずにnoteにして本当に良かったと思っています。
(2)達成感と反応の速さに驚く
1記事目を書き上げた時の感想は、Wordで文章を作成していると錯覚するほどです。更に、機能が限られているので、記事を書いたら即公開できそれだけで大きな達成感がありました。
数日後に「スキ」が1つ付いたり、フォロワーしてもらえたり、その反応の速さに驚きました。ブログでは、最初のうちは書いても書いてもだれも読んでくれない期間が続き、正直なところ気持ちが折れそうになります
(3)今後について
当初は収益を目指していたわけではありませんでした。自分の体験談を誰かに伝えたい、そんな気持ちで始めたnoteでしたが、続けるうちに「読者の興味に合わせる」「役立つ情報を届ける」という視点を持てるようになり、タイトルの工夫、冒頭の書き出し、画像の入れ方など、回数を重ねるごとに試行錯誤を繰り返しながら改善していますが、それらの一つ一つがブログのテンプレートに沿っています。
このような小さな成功体験の積み重ねが、今では大きなモチベーションになっています。noteは文章を書くことで自分を見つめ直し、人とのつながりを築ける素晴らしい場所だと実感しています。
4、AIを味方に!文章生成AIでシニアの執筆をサポート
在宅ワークの魅力は自分のペースで働けることと、新しい挑戦を楽しめることです。パソコンやスマホがあれば始められる仕事も多く、初期費用も少なく済みます。この記事では、私が実際に取り組んできた在宅ワークについてシニアでも遅くない!在宅ワーク何がある?を実践した定年後リアル体験談で説明していますのでご覧ください。
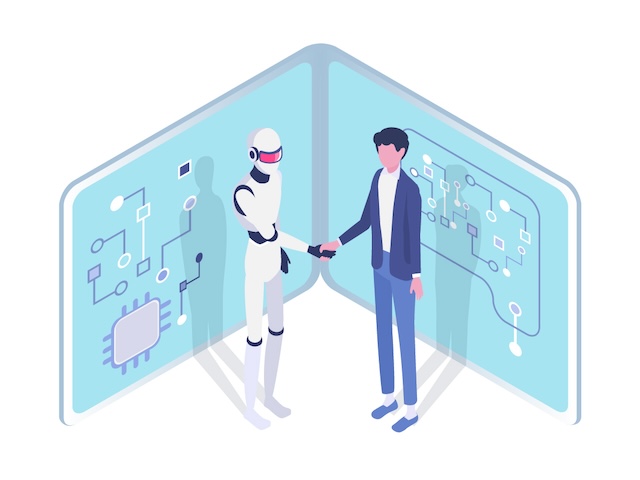
最近では、ChatGPTのような文章生成AIを使えば、記事の構成、タイトル案、言い回しの提案まで幅広くサポートしてくれるため、文章を書くハードルがぐっと下がりました。
特にシニアにとっては、時間や体力を無駄にせず、自分のペースで執筆を進められる大きな助けになります。
【体験談2】私自身もAIを活用しており、最初に「どんなテーマで書くか」「どういった構成にするか」をChatGPTに相談しています。例えば「シニアがnoteで収益を得る方法」というテーマを入力すると、見出し案や要点を自動で提示してくれます。それをベースに、自分の経験や思いを重ねていくことで、スムーズに記事が仕上がるのです。
【体験談3】文章表現に迷ったときにもAIは非常に便利です。言い回しの候補を出してくれたり、読みやすく修正してくれたりと、まるで校正のプロがそばにいてくれるような安心感があります。特に漢字の使い方や文末のバリエーションなど、自分では気づきにくい部分まで整えてくれるのも心強いポイントです。
AIはあくまで「補助役」ですが、使いこなすことで執筆のハードルがぐっと下がり、「自分にもできるかも」という気持ちを後押ししてくれます。実際に、私もAIを使うようになってから記事の更新頻度が上がり、文章構成の効率も格段にアップしました。
操作も非常にシンプルでスマホからでも入力できますし、パソコンに慣れていない方でも数回使えばすぐに慣れるでしょう。これから在宅ワークを始めるシニアにとって、文章生成AIは「時代の味方」とも言える頼もしいツールです。
5、これからnoteを始めるシニアへ伝えたいこと
noteは、特別な才能やプロのような文章力がなくても自分の想いや経験を発信できます。シニアの皆さんがこれまで積み重ねてきた人生の知恵や体験は若い世代にとっても価値ある情報です。また、定年後の暮らし方、家族との関わり、趣味の深掘り、健康との向き合い方など、日常の中で自然に身につけてきたことは、誰かの「知りたい」「学びたい」「共感したい」気持ちに寄り添えるコンテンツになります。
「これは誰にも読まれないかもしれない」と思っていた何気ない記事に「感動しました」「私も同じ気持ちです」とコメントが届いたことがありました。noteでは、そんな心の交流が生まれやすく、孤立しがちなシニア世代にとって社会とつながり続ける大切な場所となり得ます。
さらに、noteの魅力は「自分のペースで続けられること」。毎日書かなくてもよいのです。週に1回でも、月に数回でも、自分のペースで無理なく続けることで心の張りや生きがいが生まれます。
最初はたった数行の日記でも構いません。書くことに慣れてくると、自然と伝えたいことやテーマが浮かぶようになります。周囲の目を気にせず自分の言葉で綴ることで、書くことそのものが楽しくなっていくのです。

noteは、収益だけが目的の場ではなく、「伝えることを通して自分を見つめ直し、誰かの心とつながる」場所です。
焦らず、比べず、自分らしい発信を大切にしながら、ゆっくりと在宅ワークの世界に一歩踏み出してみてください。
6、シニア在宅ワークnote活用術まとめ
シニアでもnoteは簡単に始められる在宅ワークツール
ブログとの違いを理解して、自分に合ったスタイルを選ぼう
体験を元に記事を書くことで共感や収益につながります
文章生成AIは強力なサポーター、積極的に活用しよう
継続は力なり。まずは気負わず1記事から始めよう
Noteはシニアの新しい表現と収入の場として大きな可能性を秘めています
<引用元>本記事は以下のサイトからの情報を参考に作成しております。
manamina[マナミナ]まなべるみんなのデータマーケティング・マガジン
noteを活用したオウンドメディアとは?ブログとの違いを解説
note(ノート)のアプリの口コミ・評判は?【2025年2月最新】